1980年代後半に一大ブームを起こした『おニャン子クラブ』は、『夕やけニャンニャン』というフジテレビの平日17時から18時に放送された帯番組から誕生しました。
普通に考えて夕方の帯番組を毎日欠かさず観ることは難しく、おニャン子クラブに関して覚えていない、もしくは最初から知らなかった情報も多くなっています。
当時はまだビデオの普及率も低く、使われ方も主に用事があってどうしても観れないドラマなどを録画する程度で、帯番組を毎回欠かさずに録画するような人はまずいなかったと思います。
では、どんな人たちが『夕やけニャンニャン』を観ていたのでしょうか?
夕方5時から始まる1時間番組をサラリーマンが観ることは、まず不可能です。
主婦や高齢者は観れたかもしれませんが、どう考えても『夕やけニャンニャン』は主婦や高齢者向けの番組ではありません。
大学生も夕方は遊んだりバイトをしたりするケースが多いでしょうし、小学生の低学年以下は当時盛んに放送されていたアニメの再放送などのほうに興味があったと思われます。
そうなると、残るは小学生の高学年から中高生ぐらいまでしかおらず、実際に夕やけニャンニャンは中高生向けの番組であったと考えられます。
つまり、夕やけニャンニャンは極めて年齢幅の狭い層に向けて番組が作られていたということです。
そんな幅の狭い層に向けて作られた番組と、その番組から生まれたおニャン子クラブが、なぜ日本芸能史に残るような一大ブームを起こせたのでしょうか?
その問いの答えには、日本における年代別の人口が関わってきます。
日本では、第二次世界大戦が終戦した直後に多くの子供が生まれ(第一次ベビーブーム)、団塊の世代という固まった人口過密世代が誕生しました。
この団塊の世代の子供たちもまた、団塊ジュニアと呼ばれる人口過密世代となり(第二次ベビーブーム)、主に1971年度から1974年度に生まれた人たちを指します。
夕やけニャンニャン開始の1985年4月時点で団塊ジュニアは10歳から13歳、夕やけニャンニャン終了の1987年8月時点では12歳から16歳となり、まさに夕やけニャンニャンに興味を持つどんぴしゃの世代だったわけです。
本来なら、こんな年齢幅の狭い層向けの番組で大きなブームは起きないのですが、この時期に限っては、その幅の狭い層に多数の人がいるので大きなブームを起こすだけの原動力があったのです。
逆に1989年に結成された乙女塾がブレイクしなかった理由は、団塊ジュニアの年齢が上がってしまったことが原因と考えられます。
団塊ジュニアの世代は年齢幅が狭いため、3年や4年程度の時間のズレでも大きな影響が出てしまうのです。
以上のように、おニャン子クラブは日本の社会で生じた特殊な事情により大きなブームを起こし、その社会状況を上手く読んだ人が当時いたのだと思います。
当記事に登場したアイドルの記事














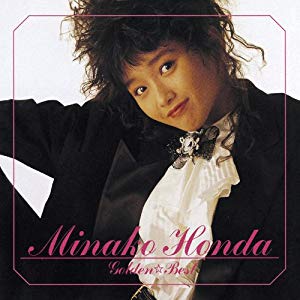








コメント